広告
「このセミ、生きてないよ」
と子供が話していました。
「セミが死んでる」と言わないで
「セミが生きてない」って言うのか。
ふと耳に入った会話から
「生きていない」と「死んでいる」の違いを
静物画を通して考えてみました。
広告
日本語で「静物画」と言われている絵画は、
英語:Still life (静止していて動かない実体)
仏語:Nature morte(死せる自然)
と言うそうです。
英語と、フラン譜で受ける印象が
違うように思います。
日本語の静物画は英語のStill lifeと
感覚が近い感じ。
冒頭に書きました子供の会話に当てはめると
「このセミ、生きてないよ」は
日本語の静物画・英語のStill lifeの感じ。
「セミが死んでいる」と言うと
仏語のNature morteに寄っているように
私は感じます。
「生きてない」は、生きている世界の
延長線上にまだある感じ。
哺乳類であるならば、まだ体温が
少し感じれられるような状態です。
かたや、「死んでいる」は、
完全に動きが止まっていて
死後の世界にいっている感じ。
三途の川を渡って、あちら側の世界へ
行ってしまったように感じます。
あくまでも私個人の感覚なので
このあたりは人それぞれでしょう。
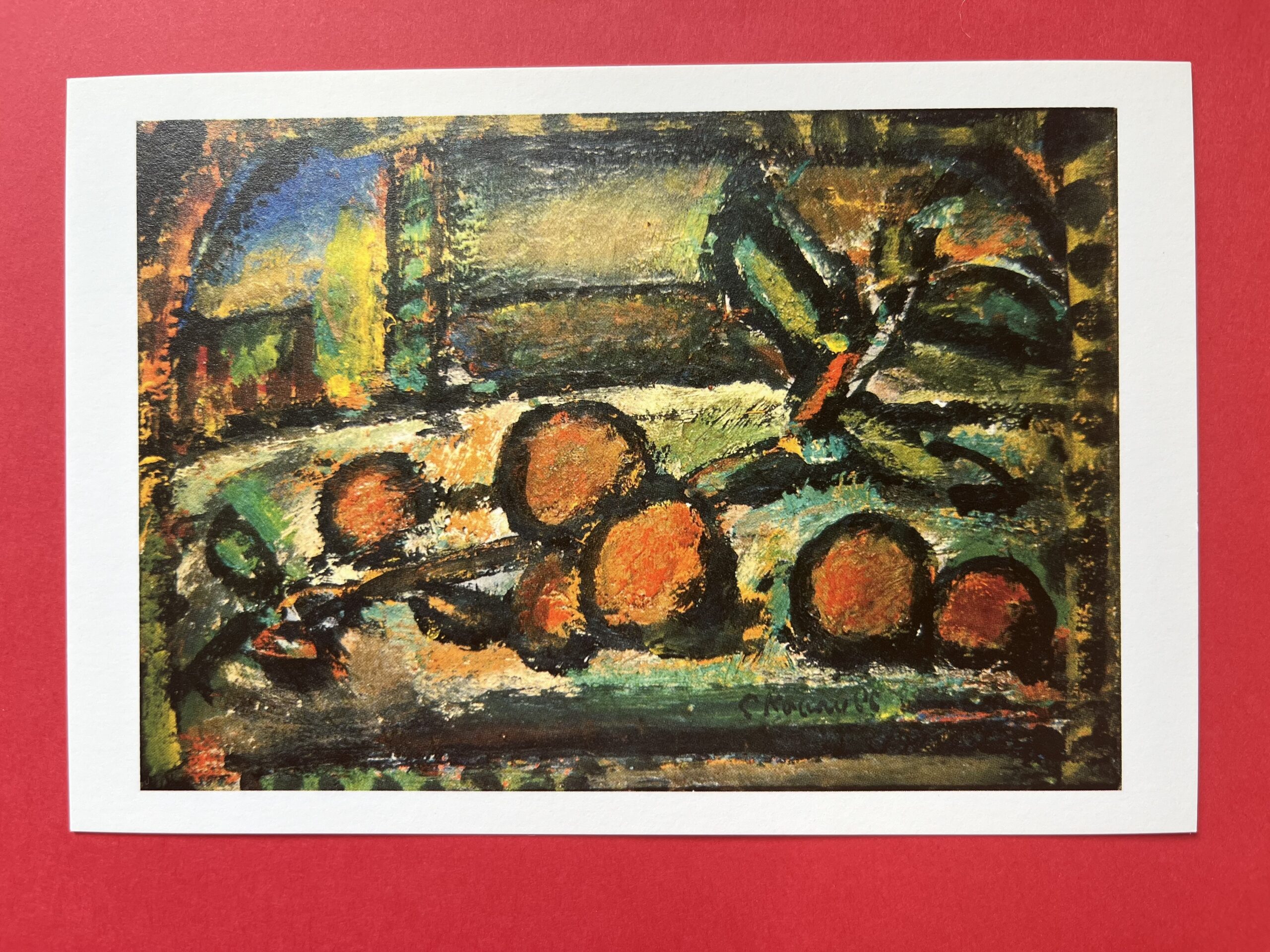
オレンジのある静物/
ジョルジュ・ルオー/
個人蔵(ルオー財団協力)
こうみてみると、日本語の
「静物画」という言葉は、
ニュートラルな感覚で、
「静物」を描いた「絵」を
的確に表す良い言い方だなと思います。
個人的には静物画を
Nature morte(死せる自然)を呼ぶ
仏語の感覚は、
ちょっと強すぎると思っていますが、
西洋画における静物画のジャンルである
Vanitas(ヴァニタス)に
その理由がありそうです。
人生の虚しさや
生きることの儚さを意味する言葉で
旧約聖書からきている言葉です。
モチーフとしては、
消えかかったロウソク、
腐りかけた果物
砂時計、ドクロなどで、
それらが描かれた静物画が
ヴァニタスとなります。
キリスト教における死生観が、
静物画に反映されているようです。
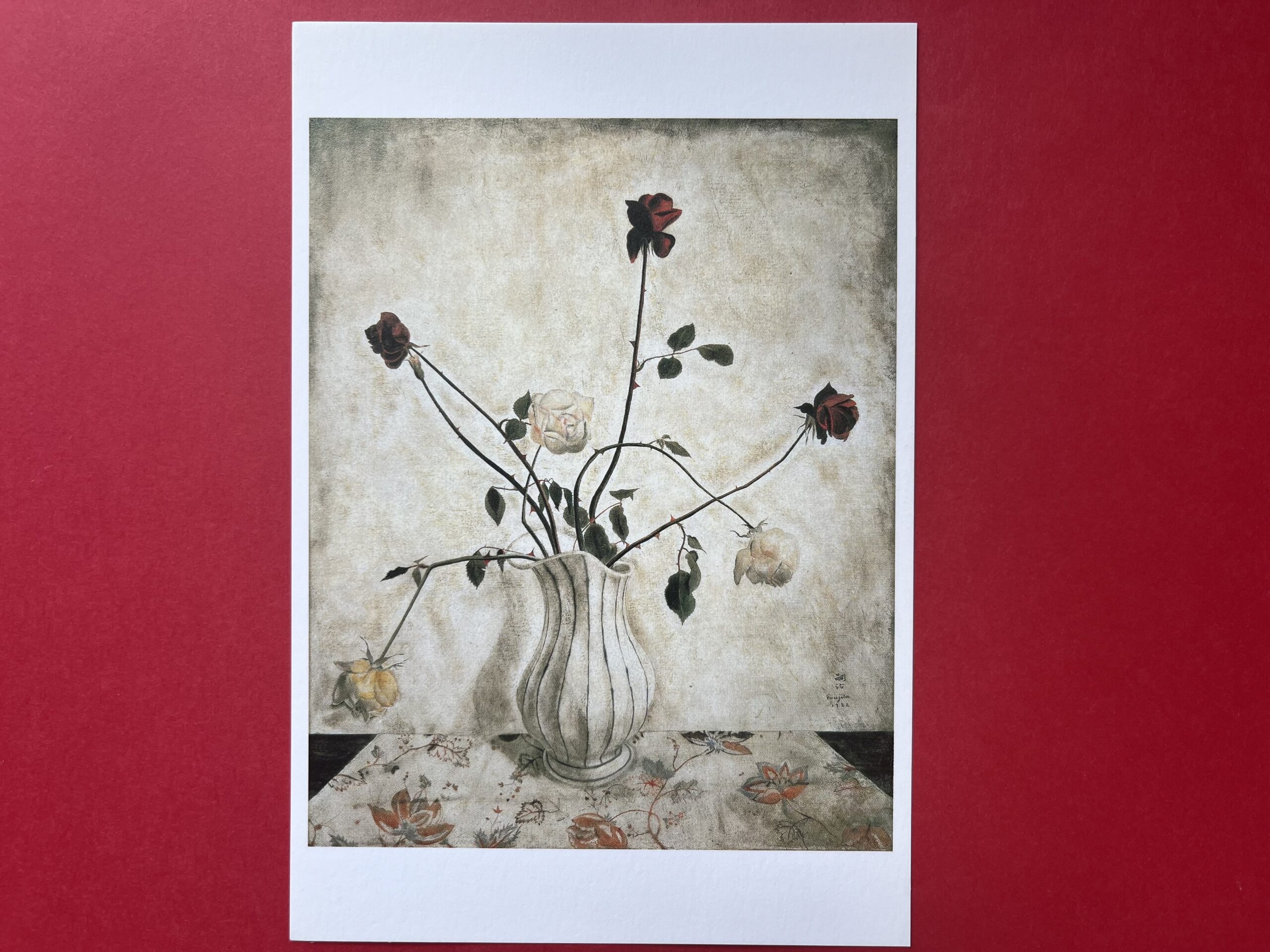
バラ/藤田嗣治/ユニマットグループ
「りんご」一つが描かれた静物画であっても
その人の持つ文化的な背景、
使用している言語によって
「生きていない」のか
「死んでいる」のか
捉え方は変わるのかもしれません。



